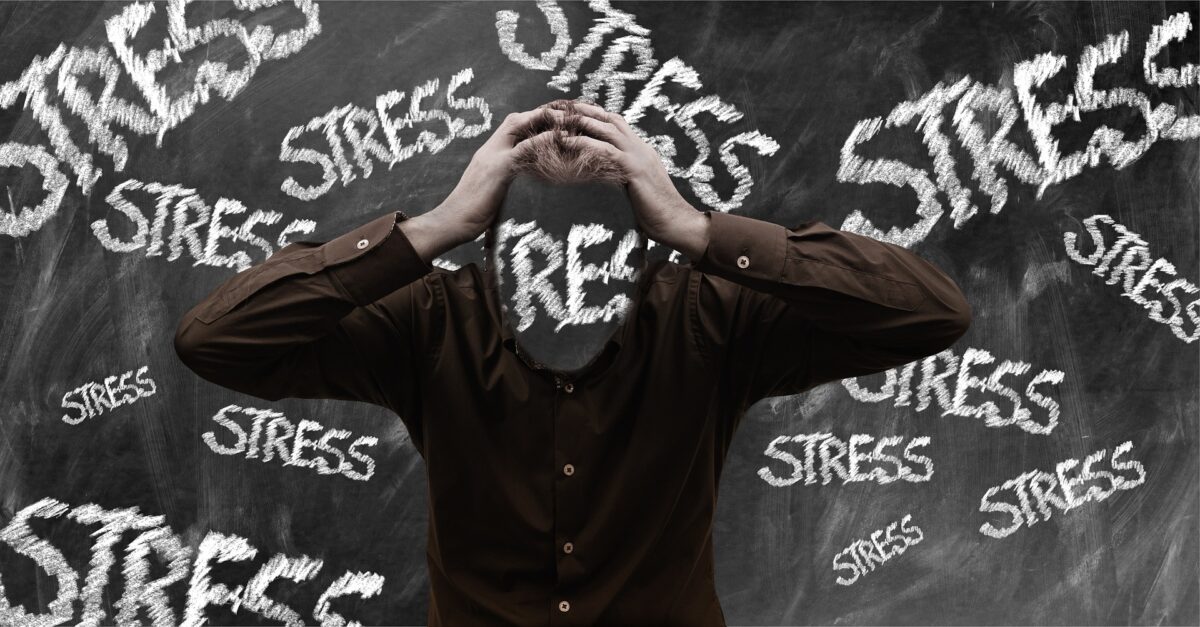「些細なことで頭が真っ白になる」「人と話すだけで疲れてしまう」「やらなきゃいけないことがあるのに、体が動かない」。
──そんな“ストレスに弱い自分”を責めていませんか?
この記事では、心理マネジメントの視点から「ストレスへの耐性が低い人の特徴と対策」をわかりやすくお伝えします。
- 「ストレスに弱い」は性格じゃない。行動の“クセ”の問題です
- 「私って、メンタルが弱いのかな…」
そう感じている人の多くは、実は“性格の問題”ではなく、“ストレスにどう対処しているか”という「行動のクセ」に課題があります。
たとえば、ストレスを感じたときに、
- 誰にも相談せずに一人で抱え込む
- 無理に我慢して乗り切ろうとする
- うまくいかないと「もうダメだ」と思考停止する
──このような傾向があると、当然ながら心がすぐに限界を迎えてしまいます。これは、心理学では「コーピング力(対処行動のバリエーション)」の不足と表現されます。
「3つのストレス対処タイプ」あなたはどれ?
心理学では、ストレスへの対処行動(コーピング)は大きく3タイプに分けられます。
1.問題焦点型コーピング
→ストレスの原因を分析し、解決に向けて行動するタイプ
2.情動焦点型コーピング
→感情をコントロールして、気持ちを落ち着かせるタイプ
3.回避型コーピング
→問題から目をそらし、気を紛らわせるタイプ
どれか一つが正解というわけではありません。大切なのは「状況によって柔軟に切り替えられるかどうか」です。コーピングの引き出しが少ないと、同じパターンに固執してしまい、ストレスを悪化させてしまうのです。
「コーピングの引き出し」を増やす実践法
では、どうすればストレスに強くなれるのでしょうか?
鍵は、“事前の準備”と“自分の取扱説明書”を持つことです。
① 自分のストレスサインを言語化する
「どんなときに疲れやすいか」「どんな状況でイライラしやすいか」など、自分のストレス反応をあらかじめ把握しておきましょう。
② “小さな対処行動”のリストを作る
・信頼できる人に話す
・5分だけ散歩する
・お風呂にゆっくり入る
・「疲れてるな」と自分に声をかける
──こうした“小さなストレス軽減策”をストックしておくと、心が折れそうな時に救われます。
③「頼る・逃げる・休む」を“戦略”と位置づける
逃げたり、頼ったりすることは、決して「弱さ」ではありません。むしろ、自分の心を守るための立派な戦略です。
おわりに──“ストレスに強い人”とは、「うまく逃げられる人」
「強くなりたい」と思う人ほど、実は“耐えること”を頑張りすぎてしまう傾向があります。
でも、本当にストレスに強い人は、自分の限界を知り、うまく対処する術を持っている人です。
心理マネジメントは、その「術」を増やす知恵です。自分を責める前に、自分を守る方法を少しずつ身につけていきましょう。
画像引用:O-DAN