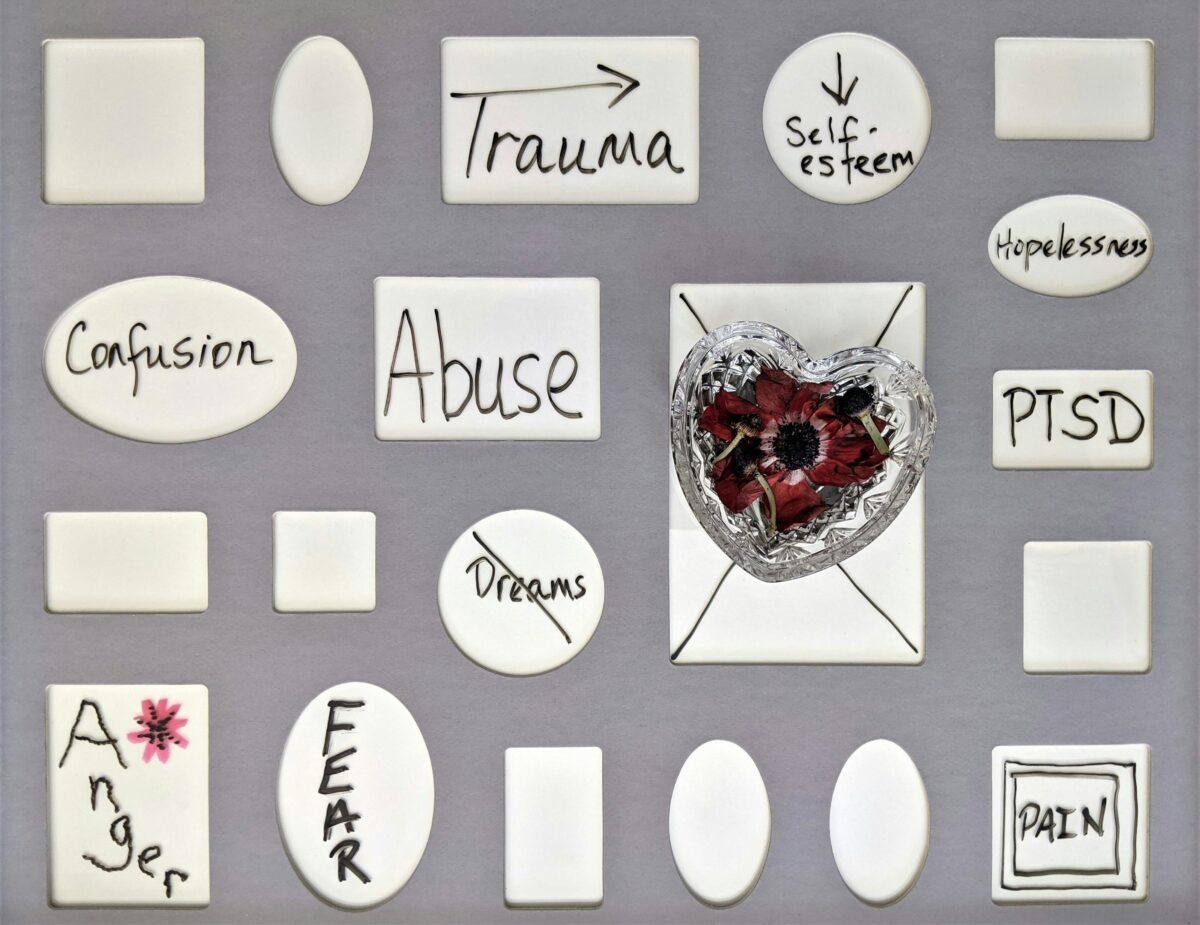先日、上司の指示どおりに作業したのに、なぜか『手順が違う!』と怒られました……
仕事をしてれば、こんな経験することもありますよね?
自分に非がないのに怒られたり責められると、心が疲れてしまいますよね。疲れすぎて辞めようかと思ったり。
yuunagi19の経験を元に、心理マネジメントの視点から 「上司を尊重しつつ、自分を守る対応法」 を解説します。
なぜ「理不尽な怒られ方」が起こるのか?
- 上司の指示があいまいだった
→ 口頭だけのやり取りは誤解が生まれやすい。 - 上司自身が手順を変えたことを忘れている
→ 人は「自分が言ったことを正しい」と思い込みやすい。 - 感情のはけ口になっている
→ 業務外のストレスを部下にぶつけてしまうケースも。
👉 つまり「あなたが悪い」わけではなく、“構造的に起こりやすいトラブル”なのです。
上司を尊重しつつ自分を守る対応法
- 感情を切り離す
「怒られた=自分の人格否定」ではなく、
「怒られた=手順の認識違い」と切り替えること。
- 記録を残す習慣をつくる
作業前に「いただいた手順をまとめました、これで進めますね」とメールやチャットで確認。
→ 証拠を残せば、再び理不尽に怒られても冷静に対応できます。
- “責めない質問”で返す
反論すると衝突するので、あくまで「学び姿勢」で。
「前回は〇〇と伺っておりましたが、今後は△△で進めるのがよろしいでしょうか?」
「勉強のために、正しい手順をもう一度教えていただけますか?」
- 第三者も巻き込む
繰り返される場合は、チーム全体で共有。
「念のため皆さんとも確認しておきますね」と情報をオープンにすると、個人攻撃を防げます。
今すぐ使える!会話テンプレ集
✅ 確認型
「申し訳ありません。前回は〇〇と伺った認識でした。今後は△△で進めるのがよろしいでしょうか?」
✅ 学び姿勢型
「ご指摘ありがとうございます。勉強のために、正しい手順をもう一度整理させていただけますか?」
✅ 共有型
「理解を深めたいので、今回の手順をまとめて他のメンバーとも共有してよろしいでしょうか?」
✅ 再発防止型
「次回以降は、作業前に私の方でまとめて確認させていただきたいのですが、よろしいでしょうか?」
👉 最初の一言は「申し訳ありません」「ありがとうございます」で始めるのがポイント。
怒りを和らげたあとに“確認”で切り返すと、衝突せずに話を前に進められます。
まとめ:尊重と防御の両立がカギ
上司を尊重する言葉で受け止める
記録や確認で「自分を守る」仕組みをつくる
責めない質問で改善姿勢を示す
繰り返されるなら第三者も巻き込む
理不尽な怒られ方を受けたときこそ、冷静に立ち回れる人は信頼を得ます。
ぜひ今回の対応法を実践して、職場でのストレスを減らしてみてください。
画像引用:O-DAN